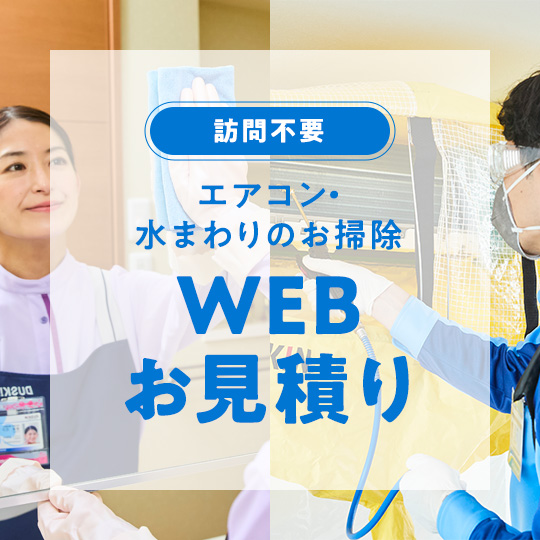この記事の目次
エアコンの除湿機能とは
エアコンの除湿機能は、室内の湿度を下げるための機能です。特に湿度が高くなる梅雨や夏場に、室内を快適な湿度に保つために活用されます。
エアコンの除湿機能には「弱冷房除湿」と「再熱除湿」の2種類があり、それぞれ異なる仕組みで除湿を行います。
弱冷房除湿は、室内の空気を取り込んで冷やし、その冷えた空気をそのまま室内に戻す除湿方法です。再熱除湿は、取り込んだ空気を冷やした後、再度温めてから室内に戻す除湿方法です。
再熱除湿は冷えた空気を再度温めるために追加のエネルギーが必要となるため、弱冷房除湿と比べて電気代が高くなる傾向があります。
エアコンの除湿機能と冷房機能の違い
エアコンの除湿機能と冷房機能は、それぞれ異なる目的で使用されます。
冷房機能は、室内の温度を下げることをおもな目的とした機能です。室内の空気を取り込み、その空気を冷やして室内に戻すという仕組みのため、一定の除湿効果も得られます。
ただし、冷房機能は温度を下げることがおもな目的であるため、湿度だけを下げたい場合には冷房機能は適していません。一方、除湿機能は湿度を下げることに特化しているため、室内の温度を大きく変えずに快適な湿度を保ちます。
部屋の湿度を下げたい場合は「除湿機能」、部屋の温度を下げたい場合は「冷房機能」と、目的に応じて使い分けるとよいでしょう。

カビはエアコンのどの部分に発生するの?

外からは確認できなくても、エアコン内部にはカビが潜んでいる場合があります。
特にどの部分にカビが発生しやすいのかを知っておくことは、エアコン掃除をするうえで重要です。
1:そもそも…なぜエアコンがカビの棲み家に?
一般的に、カビ発生率が上昇する温度環境は20~30℃とされています。これは私たちが快適に活動しやすい気温とほぼ同じですが、カビはさらに高湿度の環境を好み、60%以上の高湿度で繁殖しやすくなります。冷房使用時のエアコン内部は、カビが繁殖しやすい高温多湿の環境が整っているのです。
除湿機能を使用すると、取り込んだ空気を冷やした際に生じた水分がエアコンの内部にたまり、カビの原因となります。
また、室内に残っているホコリやゴミからカビが検出される場合も多いです。エアコンがそのような部屋の空気を吸い込むことで、エアコン内部に汚れがたまっていきます。そして、それらの汚れがカビの栄養源となり、さらにカビが繁殖することで、エアコン内部がカビにとって理想的な棲み家になってしまうのです。
2:エアコンのここをチェック!~カビが生えやすい場所~

エアコンの吹き出し口である「フィン」にカビを発見した場合、内部の「送風ファン」や「熱交換器」、ホースの間にある水のたまり場所の「ドレンパン」までカビで汚れている可能性があります。
熱交換器や送風ファンにカビが付着したままエアコンを作動させると、空気中にカビを放出することになります。すぐに取り除くのが望ましいですが、エアコン内部は構造が複雑なため手入れが難しい場所です。
エアコン掃除を自分でする場合とプロに依頼する場合の違い
エアコン内部は想像以上にカビが発生しやすい環境であることが分かりました。ただし、内部をご自身でしっかりお掃除することは故障の原因となる可能性があります。
そのため、定期的にプロに依頼することがおすすめです。
1:エアコン掃除、自分でできる範囲は?
複雑な構造を持つエアコン内部のお掃除はプロに依頼した方がよいですが、ご自身でできる範囲だけでもこまめにやっておくと、カビの発生を抑えることができます。
ご自身でお掃除できる部分は「エアコンフィルター」です。簡単にエアコンフィルターのお掃除方法をご紹介します。
まず、フィルターを本体から取り外し※、表側から軽く掃除機をかけます。次に、裏面からお湯で洗い流し、フィルターの目に詰まったホコリを押し出すようにしましょう。汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で薄め、やさしくブラシで洗うとよりキレイになります。洗い終わったら、陰干しで十分に乾かすことが重要です。
※フィルターは、取扱説明書を確認の上、正しく取り外しましょう。
2:プロならこんなところまで!
前述したとおり、ご自身でエアコン掃除をできる範囲に限りがあります。そのため、定期的にプロにエアコン掃除を依頼することがおすすめです。専用の洗剤や資器材を用いながら、ご自身では難しいエアコン内部まで分解して、くまなく洗浄できるのがプロならではの強みです。
数ある業者の中でもダスキンは、エアコン掃除のパイオニアとして30年以上サービスを提供している実績があります。
エアコン内部を徹底的にキレイにしたい方は、ダスキンの「エアコンクリーニングサービス」をぜひご利用ください。

エアコンの“キレイ”が長持ちするカビ予防方法
エアコンにカビが付着する前に予防できれば、お掃除の手間を軽減することが可能です。以下では、日常的に取り組めるエアコンのカビ予防方法をご紹介します。
こまめなフィルター掃除でカビ予防

カビ予防として常にやっておきたいのがフィルターのお手入れです。フィルターには、お部屋の空気中に漂うホコリやチリをはじめとする“さまざまな汚れ”や水分がたまり、それらがカビの栄養源となります。
カビは適度な水分と栄養分がそろった環境で繫殖しやすいため、フィルターを2週間に1回を目安にお掃除することで、カビの発生を抑えましょう。
送風運転でカビ予防
エアコン内部の水分を取り除くことが、カビ予防の基本です。つまり、「乾燥」がカビ予防における重要な要素です。
そのため、日常的なカビ対策としておすすめの方法は、エアコンの送風運転や内部クリーンの機能を使用することです。エアコンの使いはじめには、窓を開けた状態で送風運転を行いましょう。送風運転によってエアコン内部のホコリを外に出すことで、カビの付着を防ぐ効果が期待できます。
使用後にエアコン内部を、その都度乾燥させることもカビ防止のポイントです。電源を切る前の送風運転にもカビ予防効果があります。
また、内部クリーン機能が搭載されたエアコンは、設定しておくことで自動的に送風運転を行います。除湿・冷房モードで運転した後、すぐに電源を切らず15~30分ほど送風運転を行いましょう。
エアコンの除湿機能だけではカビを防げないため、プロに依頼しよう!
エアコンの除湿機能は、室内の湿度を下げることが目的です。しかし、除湿機能を使用していても、エアコン内部にカビが発生する場合があります。そのため、根本的なカビ対策としてはプロに依頼することがおすすめです。
ダスキンに依頼すれば、エアコン内部までしっかりお掃除することが可能です。
数ある業者の中でもダスキンは、エアコン掃除のパイオニアとして30年以上サービスを提供しており豊富な実績があります。技術・マナー・知識の3つの研修を受け、合格したスタッフが対応するため、技術力と接客マナーの両面で安心しておまかせください。
毎年技術研修を実施しており、最新機種のエアコン掃除にも対応可能です。エアコン内部のカビやホコリなど、ニオイの原因となる汚れを徹底的に洗浄し、カビの排出低減の効果も確認されています※1。
洗浄後は熱交換器やフィルターなど各パーツを丁寧に抗菌・防カビ処理を行うなど、気になるカビ対策も十分に実施します。サービス実施後は風速が約40%アップ※2するという効果も確認されており、快適性の向上が期待できます。
根本からエアコンのカビ対策を行いたい方は、ダスキンの「エアコンクリーニングサービス」をぜひご検討ください。
※1家庭用壁掛けタイプ(フィルター自動お掃除機能付は除く)にて測定。製品の状態により洗浄効果に差が出ます。(ダスキン調べ))
※2エアコンクリーニングを実施したお客様301名のデータ平均(ダスキン調べ))