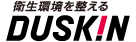2021年9月9日
【ダニ対策】布団や部屋に潜んでいるダニを駆除・予防しよう
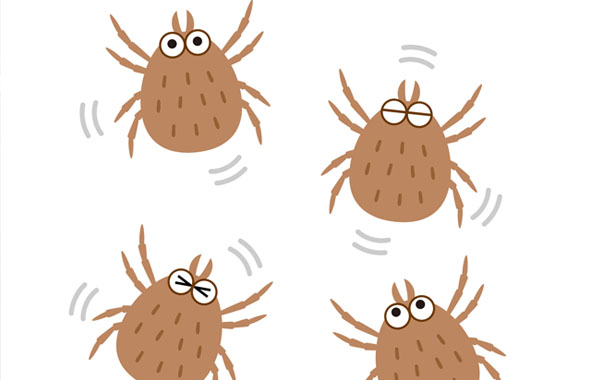
ひとたび発生すると一気に繁殖するダニ。アレルギーを引き起こしたり、刺されたりと人体に悪影響を及ぼすため、適切な予防や駆除が必要となります。
この記事では、ダニを駆除・予防するために知っておきたいことを解説します。ダニの生態に合わせて適切な駆除・予防処置を行いましょう。
目次
ダニが発生するのはなぜ?
まずは、ダニが発生する環境や時期について解説します。
ダニが発生する環境
ダニは室温20〜30℃、湿度60%以上の高温多湿な環境を好みます。また、フケやアカ、髪の毛、食べ物のカスなど、エサとなるものがある場所も大好きです。
加湿器をよく使う部屋や風通しが悪い部屋、掃除されていない部屋などはダニが発生しやすい環境となります。
ダニが発生する時期
ダニは高温多湿になりやすい6〜9月頃によく発生します。梅雨の時期は湿度が高くなるため、特に発生しやすくなります。
しかし室内で暖房や加湿器を使う場合は、季節に関係なく年中発生する可能性もあるのです。低温で乾燥しやすい冬場でも、室内で暖房を使うことで結露が生じて高温多湿になることでダニが発生します。
ダニの発生場所

ダニは布団やマットレス、まくらなど寝具でよく発生します。寝具は体温と寝汗によって高温多湿の環境になり、ダニのエサとなる皮脂やアカもあるためです。
また、頻繁に掃除しにくいソファ、カーペット、畳も湿気や熱がこもりやすいため、ダニの発生しやすい場所となります。
ダニによる悪影響
ダニが室内で発生することによる悪影響について解説します。
アレルギー
ダニの死骸を吸い込むと、アレルギー症状が引き起こされることがあります。ダニが持っている「アレルゲン」と呼ばれるアレルギーの原因物質が、人間の免疫反応を過剰に働かせてしまうためです。
アレルギーの症状には、鼻水、鼻づまり、くしゃみなどの症状を引き起こす「アレルギー性鼻炎」、呼吸をすると「ヒューヒュー」という音が喉から聞こえ息苦しさを感じる「喘息」、乾燥してかゆみを伴う「アトピー性皮膚炎」、目がかゆくなり異物感を感じる「アレルギー性結膜炎」などがあります。
ダニに刺される・吸血される
ダニに刺されたり吸血されたりすることも、ダニによる被害の一つです。しかし、全てのダニが人を刺したり吸血したりするわけではなく、ツメダニやイエダニが人に直接被害を与えます。
ダニは主に、腹部や太ももなど柔らかい部分を刺します。刺されてすぐに症状が出ないことがありますが、1〜2日経つと刺された場所が赤く腫れ、強いかゆみを引き起こし、7日ほどかゆみが続きます。
イエダニは通常ネズミを吸血していますが、宿主となるネズミがいなくなったり、死んだりすると人に吸血をするとされています。
ダニ対策① すでにいるダニを駆除
ここからは、すでに家の中に発生してしまったダニの駆除方法について解説します。
内部まで高温にする
布団を干して乾燥させることで、ダニが棲みにくい環境になります。ただし、ダニは50℃以上の環境を20分以上維持しない限り死滅しません。例えば、日に干すと布団の表面は温まりますが、内部はあまり温まらないためダニは内側に逃げてしまいます。そのため、日に干しただけでは全てのダニを駆除する効果はあまり期待できません。
布団を干すだけではなく、布団乾燥機(高温乾燥)などを使って布団の内部まで高温にし、ダニを駆除しましょう。
燻煙剤を使用する
燻煙剤は、室内の隅々まで殺虫成分を含んだ煙を行き渡らせるため、隠れたダニも駆除できます。ただし、食品や食器などに薬剤が付かないように養生したりペットや熱帯魚などを移動するなど事前に準備が必要ですので、よく使用上の注意を読んでください。燻煙剤の使用後は窓やドアを開けて換気し、掃除機をかけてダニの死骸を除去しましょう。
掃除機をかける
畳や布団、カーペットに潜んでいるダニは、掃除機をかけて駆除しましょう。ただし、生きているダニは繊維にしがみつくため、掃除機ではほとんど吸い取れません。布団を乾燥させたりしてダニを駆除した後で掃除機をかけましょう。
ダニ対策② ダニが寄ってくるのを予防する

続いて、ダニを寄せ付けない方法をご紹介します。
ダニを予防するスプレーを使う
ダニ予防に有効なのは、ダニ予防スプレーです。
スプレーはまくらや布団などの寝具、ソファなどに吹き付けておくことで、ダニの発生を予防できます。ただし、まくら・布団用のものか用途を確かめてご使用ください。
高温多湿な環境を作らない
生活環境の中に高温多湿な環境を作らないことで、ダニ予防につながります。高温多湿にならないようにするためには、換気が欠かせません。特に湿度が高くなりやすい梅雨の時期などは、除湿機やエアコンのドライ機能を使って室内の湿度を下げましょう。
また、エサとなるような汚れ(フケ、アカ、髪の毛など)は残らないよう、こまめに掃除しておくことも大切です。
シーツ・カバーを定期的に洗濯する
シーツやカバーは人の肌が触れる場所のため汗や皮脂がたくさんつきやすく、ダニにとって居心地の良い場所になっていることがあります。定期的に洗濯し、ダニの好物をなくすことで、ダニを近寄りにくくしましょう。
増えすぎたダニの駆除・予防はプロにご相談を!
ダニは高温多湿でエサのある場所に発生し、人体に悪影響を与えます。室内の湿度はできるだけ下げた状態にし、こまめに掃除することが予防につながります。
しかし、ダニを肉眼で見ることは難しく、繁殖力も高いため、気がつくと大量発生し、広範囲に生息してしまっていることがあります。自力では駆除が追いつかない、という方はプロに任せましょう。
ダスキンでは、「ダニ駆除サービス」も承っております。ダニが発生している現場に駆除のプロが伺い、発生状況や範囲を調べた上で見積りし、駆除の作業内容を提案いたします。詳しくはコンタクトセンター(0120-100-100)までお問い合わせください。